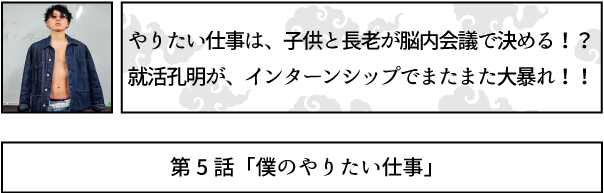
就の後ろに立つ大男は、素肌にデニムジャケットをはおり、ジョンレノンのような丸サングラスをかけていた。

「孔明先生、この方とお知り合いなのですか」僕は尋ねた。
「ああ。この男は、就活神・リクルーティス。元はギリシアで神様をしておったのだが、ギリシア金融危機の煽りで失業してな。わしの助手として働いておったのだ。
だが、内定を取らせるためには手段を選ばぬやり方があまりに汚くて、破門にしたのだ」
「おーおー。人聞きの悪い。俺はただ、顧客の要望に応えてだなぁ――」リクルーティスが口を挟んだ。
「黙れ!お前まさか、まだあんなことをしているんじゃないだろうな」
「ぜははは!さあなぁ……」
リクルーティスが意味深な笑みを浮かべた。
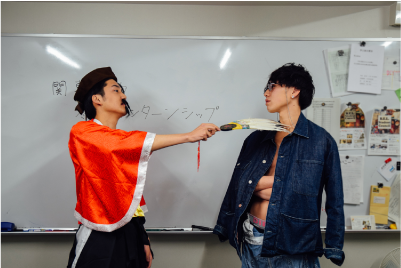
「孔明さん、お互いこの道を行く限り、また会うこともあるだろうよ。せいぜいあんたも、失業には気をつけな」
そう言い残し、リクルーティスは姿を消した。
「ふんっ。腐れ外道め……」孔明は吐き捨てるように言うと、会場を出て行った。
――時刻は午前10時、会場前方に立つ男性が口を開いた。
「皆さん、おはようございます!関東電力のインターンシップへ、ようこそ。司会進行の野上と申します」
インターンの開幕だ。
午前中は、インフラ業界や関東電力についての説明だった。
2時間程で午前の部は終わり、休憩を挟んで午後の部が始まった。
「突然ですが質問です。この中で『やりたい仕事』があると言う人は手を挙げてください」
野上さんが学生を見渡した。手を挙げた学生はわずかだった。
「うん。そうですよね。やりたい仕事って、案外見つかりませんよね。そう思って今日は、特別講師の方をお招きしました。拍手でお迎えください。
就活界のカリスマ、就活孔明先生です――」
じぇじぇじぇ!僕は耳を疑った。
「やぁ、諸君!わしが有名な就活孔明だ」本当に孔明が出て来た。覇気をまとえば、孔明は誰にでも姿を見せることが出来る。
学生達は、この髭オヤジは誰だという顔をしているが、孔明はお構いなしに話を始めた。
「さて、今からやりたい仕事の見つけ方を伝授するわけだが、まず、諸君の中にある勘違いを正すところから始めよう。そこの君――」
孔明が、最前列の女子学生を指した。
「君は、やりたい仕事がないということだが、企業の説明を聞いて、やってみたいなと感じたことは、本当に一度もないか」
「いえ……。そう言われると、そんなことはありません。
さっきも野上さんのお話を聞いて、社会を支えるために働きたいなって感じました」
「おや?ではなぜ、手を挙げなかったのかな」
「うーん……。そうですねぇ。いいなとは思ったんですけど、別にそこまでの確信はないっていうか。『絶対にこれだ!』とまでは思えないんです……」
それを聞いて、孔明は満足そうに頷いた。
「諸君。聞いたかな。彼女こそ、まさに就活生の典型だ。
やりたい仕事がないとは言いつつ、別に全く無いわけではないのだ。
でも、本当にこれでいいのかという不安が付きまとい、心底やりたい!とまでは思えない」
皆が、自分もそうだと頷いた。
「だから、やりたい仕事がない人が本当に学ばなくてはならないのは、やりたい仕事を『見つける』方法ではなく、やりたいと感じた仕事を『自分自身に対して納得させる』方法なのだ」
なるほど……。自分自身を納得させるなんて考え方したこともなかった。
「その方法を学ぶためにはまず、自分の頭の中で起きていることを理解しなくてはならない。
諸君、頭の中に『直感』と『理性』という2人の小人が住んでいると想像してくれ。
直感は子供のように無邪気で、理性は長老のように思慮深いイメージだ」
僕は自分なりの子供と長老をイメージした。
「2人にはそれぞれ違う役割がある。
直感の役割は、とにかくやりたいことを見つけてくることだ。例えば、『情熱大陸』を見て『こんな仕事がしたい!』と感じたら、それは直感が働いた証拠だ。
一方で、理性の役割は、直感が見つけてきたことを、実行すべきかどうかを判断すること。人生には限りがあるので、直感の言うことを全て聞き入れることは出来ないからな」
「なんか若手社員と上司みたいですね」僕は言った。
「まさにそんな感じだな。まるで会社のように、脳内では、直感と理性による企画会議が日々行われている。
そして、彼女が言っていた『絶対にこれだ!』という確信は、直感が理性の説得に成功して初めて得られる感覚なのだ」








