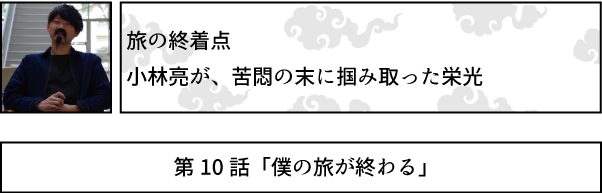
「――最終面接を終わります」
進行役の平田さんが言った。その一言で、一気に肩の力が抜けた。
僕はお辞儀をして、役員会議室を出た。
「お疲れ様です」
女性人事担当の櫻野さんが言った。
「面接結果は、3日以内にご連絡しますね。本日はありがとうございました」
僕は、深々と礼をして会社を後にした。
「しかし、まさか小林と一緒になるとはな」就が言った。
「こっちのセリフだよ。俺、なんか変じゃなかった?」
「全然。しっかりと自分の考えを言って立派だった」
「ありがとう。就こそ、何としても入社したいって情熱が伝わってきた」
「そうか」就はそう言って微笑んだ。
「就、ライバルのお前がいたから俺はここまで頑張ってこられた。本当にありがとう」
「何だよ。改まって」
「……。多分、今日の面接に通過するのは、よくても俺らのどちらか一人だろう」
「ああ」
「でもさ、どんな結果になっても、これからも仲良くしような!」
「そんなの当たり前だろ」就は笑った。
「孔明先生、ただいまー」僕は家に着いた。
……。いつものように返事がない。僕は何だか胸騒ぎがして、急いで自分の部屋に駆けこんだ。だが、部屋は真っ暗だった。おかしい。僕は心当たりのある場所を順に探したが、どこにも孔明はいなかった。次の日も、その次の日も孔明は帰ってこなかった。
辛いことは続くもので、3日経っても、毎朝放送からの連絡は無かった。つまり、僕は不合格だったのだ。ESから最終面接まで、毎朝放送の選考が走馬灯のように思い出された。あと少しで手中に収まりそうだった内定は、幻と消えた……。就はどうなったのか気になったが、僕は怖くて聞けなかった。どんな結果になっても恨みっこなしと約束したが、やはり自分だけが落ちるのは嫌だった。
僕は、面接に落ちたショックと孔明が消えた喪失感で、就活を続ける気力を失った。
それから一週間後――
「お兄ちゃん!お兄ちゃん!大変……!」佳林が勢いよく僕の部屋の扉を開けた。
「どうした、いきなり……」
「これ!」そう言って佳林が僕に一通の手紙を渡した。
手紙に目を留めると、差出人は「就活孔明」と書かれていた。僕は破れんばかりの勢いで封を開けた。
亮へ
最終面接、お疲れ様。突然いなくなってすまなかった。弟の諸葛孔明の体調が突然悪化して、わし本来の時代へ帰らねばならなくなったのだ。最後までお前の就活を見届けられなかったのは本当に残念だ。
この手紙が、本当に最後の講義となる。心して読んでくれ。
これまでお前には、就活に関する様々な理論を教えきた。お前はそれを一つ一つものにし、見違えるほどに成長した。しかし、最後に一つ言っておかねばならぬことがある。それは、「就活には、理論ではどうにもならないことがある」ということだ。
心理学者のアドラーは言った。「人間の悩みの100%は対人関係である」と。その言葉を借りるならば、就活もまた100%が対人関係だ。残念ながら、人類は未だ、対人関係の全てを理論化するには至っていない。ゆえに、就活には常に不確実性が付きまとう。学歴やコネは言うに及ばず、「何となく気に入らない」といった理由で評価が下されるのが就活なのだ。あぁ!何て理不尽なのだろうか。
人は、自分達が理解出来ない人智を超えた存在を「神」と名付けた。そして、就活における不確実性を「相性」と命名した。全てを理論で解明したいと考えるわしにとって、相性の存在ほど受け入れ難いものはない。「就活は相性」なんていう無責任で生産性のないアドバイスには吐き気がする。
しかし……、それは世界の真実なのだ。
その真実を受け入れない限り、就活生はより一層苦しむことになる。相性の存在を認められない者は、就活が上手くいかないとき、自分を否定してしまう。自分は人より劣っているのだと。そして、自己否定の螺旋に迷い込み、やがて己自身を滅ぼしてしまう。お前は、そうなってはならないぞ。極限まで理論武装した上で、相性という神の存在を受け入れるのだ。
亮、毎朝放送に内定したか。もしそうなら、本当におめでとう。しかし、仮にダメでも、それは毎朝放送とは相性が合わなかったというだけのことだ。なに、会社は毎朝放送だけじゃない。この世には、本当にたくさんの会社がある。そしてその中には、お前を必要としてくれる会社が必ず存在する。それもまた世界の真実なのだ。
辛くなったときは、この手紙を読んでくれ。たとえ、何人の面接官がお前のことを否定しようとも、お前の価値をわしは疑わない。お前は最高の弟子だ。
さぁ、恐れず進め!栄光は、すぐ目の前にある。
就活孔明
「孔明先生……」
僕の目からこぼれた大粒の涙が、手紙の文字を滲ませた。
ふさぎ込んでいる場合ではない。もう一度、頑張ろう。僕の心が再燃した。











